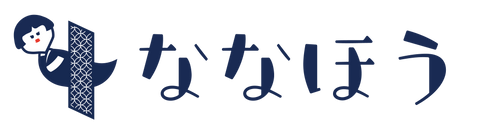Concept
キモノは、いつもの時間に プラスして幸せを届けてくれます。
大切な人との絆を深めくれます。
ななほうは、気軽に きものを 楽しんでいただけるよう
日常に彩りをお届けできるよう お手伝いさせていただきます。
作り手のぬくもりと一緒に キモノを届けしていく
オンラインの小さな着物屋です。
- 理念 -
キモノで楽しい時間をお届けし、
日本のものづくりを伝えていきます。
一、キモノの愉しさ、日本文化に触れていただく事で
日本の繊維業界を見直していただくきっかけを作り
豊かな社会をつくっていきます。
刑部 優美帆

活動・メディア掲載
1988年 静岡県湖西市生まれ
2013年~静岡県浜松市呉服屋勤務
2014年~(一社)イマジンワンワールド設立時入団兼事務局
福岡県久留米市呉服屋勤務
2015年 |TEDxShimizu2015登壇
2017年5月12日|朝日新聞(地域版)「久留米絣でキリバス表現」
2017年6月21日|中日新聞(地域版)「湖西市出身・刑部さん東京五輪へプロジェクト」
2017年6月20日|静岡新聞(地域版)「湖西市に協力求める」
2017年6月25日|毎日新聞(地域版)「着物プロジェクトに参加 久留米高英語科2年」
2017年6月26日|西日本新聞(地域版)「久留米高生 着物づくり挑戦」
2017年7月10日|中日新聞(全国版)「この人」
2017年7月19日|東京新聞「この人・五輪向け各国イメージの着物作る」
2017年12月8日|朝日新聞(福岡版)「五輪の華 着物にマレーシア」
2018年8月18日|fumika.浴衣コーディネート担当
2018年1月30日|静岡新聞(地域西)「母国の文化 湖西で紹介」
2018年1月29日|中日新聞(県内版)「KIMONOに友好の華」
2020年4月31日|福岡県久留米市呉服屋退社
2021年6月 |久留米絣工房の見学開催
2020年6月4日 |西日本新聞「久留米絣工房の見学参加者を募集」
2020年9月 |静岡県湖西市へ転居
2020年9月5日 |東京ガールズコレクション2020A/W「文化庁・日本博」衣装協力
2020年12月12日13日|千葉県船橋市「きらくに きものを 楽しむ久留米かすり展」
2020年12月11日|朝刊東京新聞千葉県版 掲載
2021年3月 |静岡県西部エリアにて出張着付け開始
2021年4月21日|日本橋三越「イタリアを楽しむ 和を楽しむ」 2021年4月23日|朝刊読売新聞都内版 掲載
2021年5月 |静岡県西部エリアにて着付け教室開始
私の日本人としてのアイデンティティの欠落
私は高校卒業後、自動車関係の工場に7年務めており週末知人がオーナーをする外国人バーの手伝いをしていました。
私は「英語が話せられるようになったらいいな」
「海外のことを知れたらいいな」と海外に目が行っていたのですが、
勤めてみるとお客様の外国人の方々は日本についてよくご存じで、
また自国の文化や国についてもいろいろと教えてくれました。
私はというと自分の国の誇れることも、
語ることもできずに恥ずかしかったのを今でも覚えています。
それではいけないと思い自国の文化を学ぼうと、
唯一興味のあった「着物」を学ぼうと思い着付け教室に通い始めました。
自国の文化を理解することで、相手の文化をも理解することができ
より良いコミュニケーションをとれるものだと感じました。
着物の工房の背景
当初着物についてネットで調べてみると約30工程以上を経て作られること、
また最低でも半年はかかることを知り、
美しいものには理由があるという事を知りました。
私は実際に物が作られている場所を見てみたいと、
夏の暑い日に京都へ着物を作る工房を訪問しました。
そこでは70代の男性の方がクーラーもつけない部屋で着物を作られていました。
「着物を作るには作品に影響してしまうので夏でも冷房を入れられず、
冬でも暖房を入れられない。」とお話ししてくださいました。
また年配の方が多いと思っていましたら
「一人前になるのには短くても10年かかる。
若い者はコンビニで働いた方がお金になる。と辞めて行ってしまう。」
という事でした。
私はものづくりを目の前に感動したとともに、とても悲しかったのを覚えています。
その時に勤めていた工場を退職すると決意し、
この文化を伝えるために呉服屋へ転職しようと決意しました。
着物のハードルの高さ
呉服屋に勤めてみるとそこは着物のハードルを高く持つお客様が多くいらっしゃいました。
「箪笥の肥やしになっている」「着るとき(着付け)にもお金がかかり、着た後(お手入れ)にもお金がかかる」「自分で着ることができない」「必要な小物が分からない」
消耗品でなければ、普段目にするものでもないことから
ハードルが高く感じられるのだと思いました。
その反面着物に興味のある方は多くいらっしゃいます。
皆様の「着たいという気持ち」とお持ちなのに「着物に触れる機会がない・知識を得る場所がないこと」が問題なのだと感じました。
久留米かすりとの出会い
私は2014年に福岡県の呉服屋に勤め、同時に世界に着物を発信する(一社)イマジンワンワールドKIMONOプロジェクトの事務局として活動しはじめました。
プロジェクトでは着物産地、全てに参加していただくall Japanというコンセプトから私もたくさんの産地のものづくりを勉強させていただきました。
プロジェクトでは主に絹(シルク)素材の産地の参加でしたが、2015年に地元の産業物でもあることから久留米かすりも参加していただく事になりました。
私は、制作担当として『藍生庵 松枝哲哉先生・小夜子先生』と多くの時間を過ごさせていただく事になり、藍・織りの魅力、また作り手の感性に刺激を受けました。
2019年木綿の着物の販売
勤めていた呉服屋では絹物のみ取り扱いになり、木綿の久留米かすりの取り扱いはありませんでした。
理由は呉服業界でいうと絹と木綿の違いは大きくあるからです。
洋服で例えるのであれば、絹は品の良いドレス、ワンピース。
木綿はカジュアルなジーンズジーパンです。
固定概念がなかった私は、着物のスタートにハードルを下げて楽しんでいただける久留米かすりの販売を企画しましたが3年間企画が通ることはありませんでした。
その理由としてはお店のコンセプトと違う事でした。
一度は納得したものの、着物のハードルを下げて楽しんでいただくご提案をしたいと思い企画を練っては上司に提案し、2019年に取り扱いを受け入れていただけることになりました。
お客様からは「家で洗うことができるので気軽に着ていける」「着付けの練習にも使える」などお言葉をいただきとても嬉しかったです。
ものづくりを伝える
2021年4月に7年間勤めていた呉服屋を退社しました。
これから自分に何ができるか?と考えた時
着物に興味を持った「ものづくりを伝えていこう」と決意しました。
着物は普段触れること、学ぶ場所がないからハードルが高く感じる。
「素材・品質・価格」しっかりとお伝えした上でお客様に楽しくお求めいただけたらと思っています。
着物は節目をより良いものにしてくれる
私は「節目」という日本文化はとても大切なものだと思います。
例えば、節目をもっている植物と言えば、「竹」があります。竹は、1日に1m以上伸びることもある成長の早い植物です。しかし、ただ上へ上へと伸びていては、自分自身を支えきれなくなってしまいます。そこで、自分を支えるために「節目」があるのです。強い風や雨、雪があっても、折れずに耐えられるのはこの「節」があるからなのです。逆に言えば、「節」がしっかりしていないと、竹はまっすぐに伸びることはできません。
このことは竹に限らず、私たち人も同じです。
生活においての「節目」は、1年という長い節目もあれば、学期や毎月、そして毎日といった「節目」 もあります。これまでの自分の生活を振り返り、これからの目標を定め、強いしっかりとした「節」を作りことは、家族との絆、人への繋がりへの感謝を改めて感じることができます。
着物は着ることで礼を示すなど、日本ならではの奥ゆかしさがあり、大切な人との時間をより良いものに深めてくれます。着物を着る意味などもお伝えしていきたいと思っています。
久留米かすりきもの専門
久留米かすりは「家で洗える」「衣替え不要、オールシーズン着れる」「丈夫な素材」「気軽に着ていける」というとてもカジュアルな着物に相応しい素材です。
着物初心者の方にも「着物の着かた」「着物のTPO」「着物の価値」など着物の入り口にお持ちいただき、日常に彩りをお届けできたらと思っております。

(一社)イマジンワンワールドKIMONOプロジェクト「100か国完成披露式典」2018年4月29日

2015年6月29日|西日本新聞「世界は一つ着物で表現」

2015年 TEDxShimizu2015登壇

2017年6月25日|毎日新聞(地域版)「着物プロジェクトに参加 久留米高英語科2年

2017年7月10日|中日新聞(全国版)「この人」

2017年7月19日|東京新聞「この人・五輪向け各国イメージの着物作る」

2018年1月29日|中日新聞(県内版)「KIMONOに友好の華」

2018年1月29日|中日新聞(県内版)「KIMONOに友好の華」

2018年8月18日|fumika.浴衣コーディネート担当

2020年6月4日|西日本新聞「久留米絣工房の見学参加者を募集」

2020年12月12日13日|千葉県船橋市「きらくに きものを 楽しむ久留米かすり展」
12月11日朝刊東京新聞千葉県版 掲載
2021年4月21日|日本橋三越「イタリアを楽しむ 和を楽しむ」 4月23日朝刊読売新聞都内版 掲載